
以下では、説明VIDEO(損益_会社見える化_Gshot)の補足説明を行っています。
なお、「基本操作」VIDEOにおいて、「損益」グラフを利用している関係上、「基本操作」VIDEOにおいて、「損益」の一部の説明が行われています。ここでは重複を避けた説明にしてありますので、「基本操作」VIDEOも合わせてご覧ください。
|

|
 「損益」の基本は、「売上」と「利益」の金額です。 「損益」の基本は、「売上」と「利益」の金額です。 |
グラフで表示される「利益」は「粗利」と「最終利益」です。「粗利」は、例えば、60円で仕入れたものを100円で売った場合の差額40円のことです。通常は会計上の「売上高」から「売上原価」を控除した「売上総損益金額」に等しくなりますが、「売上原価」に固定費が含まれている等の理由により、経営管理上、「粗利」を調整すべき場合は、Gshotデータ作成時に、調整処理を行います。「最終利益」は会社全体のグラフでは、常に会計上の「当期純利益金額」に等しくなります。 |
 |
 「損益分岐」グラフも経営管理上は、非常に有用なグラフです。 「損益分岐」グラフも経営管理上は、非常に有用なグラフです。 |
「損益」VIDEOの説明には出てきませんが、Gshotには上記の一般的な損益グラフの他に、「損益分岐」グラフがあります。直感的な表現では、上記の一般的な損益グラフは、「売上」から「費用等」を控除した残りが「利益」である、ことを表現しますが、「損益分岐」グラフは、「粗利」で「固定費」を回収した残りが「利益」である、ことを表現します。両グラフは表現方法の違いに過ぎませんが、経営管理上は
非常に有用なグラフです。「損益分岐」グラフについては、pdf(損益)にて説明を行っていますので、ご参照ください。 |

|
 損益は、「率」での検討が有用です。 損益は、「率」での検討が有用です。 |
「損益」は売上を100%とした場合の、「率」での検討が有用です。単月値(売上・利益)をベースに率表示すれば、季節変動による利益率の変動(月別利益率変動)が確認でき、更に横軸を「年月順」から「月別順」にすると、その変動をより明瞭化できます。また、年度累計値(売上・利益)をベースに率表示すれば、時系列の利益率変動トレンドが確認でき、対前期同月値(売上・利益)をベースに率表示すれば、そのトレンドをより明瞭化できます。一般的に同じ事を繰り返している限り、「利益率」は低下していきますので要注意です。 |
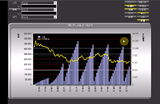 |
 「売上」は、「数量」と「単価」に分解して検討する必要があります。 「売上」は、「数量」と「単価」に分解して検討する必要があります。 |
業種にもよると思いますが、多くの経営者は「売上額」とともに「数量」も管理しており、その重要性をご理解頂いている事と思います。「数量」は既に経営者が会社毎に、部門毎に利用している数量(客数、請求件数等)を利用します。会計データで数量が管理されていない場合は、別途数量データをGshotで合成します。「単価」は「売上」と「数量」から事後的に算出される数値です。経営管理上の「損益」管理は「数量」管理までを含むべきと考えております。 |
 |
 「数量」も部門別に分解します。 「数量」も部門別に分解します。 |
「数量」も分解したい特定の月のグラフ(棒)をクリックすると、「損益金額」同様その月の部門別数量グラフが表示されます。もちろん、部門毎に、別種類の数量(例えば、客数と請求件数)で管理されている場合は、それを並べても意味がありませんので、「管轄」等を利用して同一種類の数量を利用している部門を抽出表示します。 |
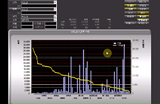 |
 「数量」も横軸の並び順を変更してみる。 「数量」も横軸の並び順を変更してみる。 |
時系列(年月)グラフも年月順を月別順に、部門別損益グラフも売上順を利益順に、横軸の並び順を変更することで、同じ基礎数値を利用しているグラフであるにも関わらず、全く違った見え方になり、そこで表現できる情報も違ってきますが、「数量」グラフも同様に、数量順グラフを単価順グラフにするだけで、違った情報、気づき、を提供する経営管理資料(グラフ)になります。 |
 |
 「数量」と「単価」も対前期同月比を見てみる。 「数量」と「単価」も対前期同月比を見てみる。 |
「数量」も「損益金額」同様に、対前期同月比グラフを見てみると、短期での増減トレンドを明瞭化できます。「数量」と「単価」グラフ共にプラス方向に伸びているのが最高の形で、両方のグラフがマイナス方向に伸びているのが最悪の形で、いづれか一方のグラフがマイナス方向に伸びているのがその中間形です。これも、更に横軸を「数量順」や「単価順」にすると、検討を要すべき部門がより鮮明になります。 |
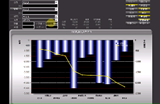 |
 更に「数値」で絞り込みを行う。 更に「数値」で絞り込みを行う。 |
「会社」「管轄」「部門」で要検討部門を抽出することはできますが、更に、ある一定値以上の「数量」と「単価」で、各部門の絞り込みを行い、見たい部門のみを表示することもできます。例えば、数量1000件以上、単価5000円以下の部門を抽出する場合等です。また、同条件でグラフを対前月同月比にすれば、数量1000件以上増加、単価5000円以下低減の部門が抽出されます。つまり、絞り込み条件に使う数値は、グラフの数値によって、異なった意味になり、組み合わせ次第で、種々の抽出を行うことができます。 |
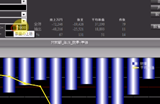 |
 抽出部門の構成比 抽出部門の構成比 |
「会社」「管轄」「部門」で抽出した部門を全体として、「数量」と「単価」数値で更に絞り込んだ部門が、どの程度の割合(構成比)になるのか、という情報も有用です。構成比には、「件数」、「売上」、「数量」、「単価」の情報があります。例えば、ある「管轄」の部門が10部門あって、その売上合計が1億円、数量が1万件、平均単価が1万円であった場合に、対前期同月比で800件以上数量がマイナスした部門を抽出したところ、3部門、その売上合計が4千万円、数量が5000件、平均単価が8000円、等の数値情報と各構成比率が同時に表示されるということです。 |
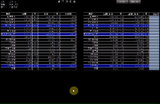 |
 利用者が複数の「会社」「年度」を跨いだデータを集計・加工できる 利用者が複数の「会社」「年度」を跨いだデータを集計・加工できる |
「数値」を見ると「グラフ」が見たくなります。一方で、「グラフ」を見ると「数値」が見たくなります。これは「損益」に限った事ではありませんが、Gshotのグラフは全てその基礎数値を表示できます。そして全ての「数値」はダウンロードして利用者が2次加工できます。Gshotは、「会社」や「決算期」の垣根を跨ぎますので、複数の「会社」「年度」を跨いだデータを瞬時に集計でき、そのデータを利用者が使うことがでます。 |
| |
|
以上で、補足説明を終わります。
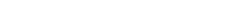
|
![]()
